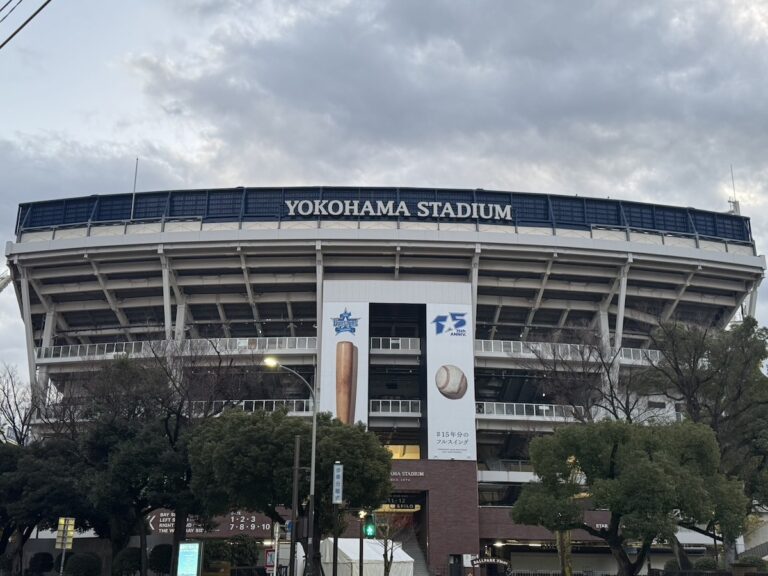来春の選抜大会から高校野球で指名打者(DH)制度が導入されることが判明した。理事会で承認され次第、正式に高校野球の公式戦で初めてDH制が採用されることになる。
プロ野球は今シーズンも“投高打低”に。セ・リーグは前半戦終了時で3割打者不在で、初の打率2割台首位打者も?
東京六大学や関西学生野球連盟でも来春から導入されるため、高校野球以上のカテゴリーでアマチュアのリーグ全てがDH制が採用されることとなる。
そして、ついに最後まで残ったのがセ・リーグ。国内のリーグのみならず、各国プロリーグや国際大会では基本DH制が用いられているため、ほぼ世界的に見てもほぼ唯一DH制を採用していないリーグとなる。
かねてから議論はされてきた。原辰徳氏が巨人監督時代の20年オフにDH制導入を提案するも、セ・リーグ他5球団からの反対を受けたこともある。
今年に入ってからも1月の12球団監督会議でソフトバンク・小久保監督が交流戦での試験的な導入を提案したが、賛成・反対と意見が分かれていた。
メリットとしてはレギュラーが9人から10人なることで野手の出場機会の増加が図れると共に、投手が打席に立つ必要がないため負担軽減と故障防止につながると考えられている。
セ・リーグにおいて反対されている主な要因が戦術面。
岡田彰布氏は昨年の監督会議の際に「監督が楽すぎる。ピッチャー(の打順)が回ってくるとか回ってこないとか、そういう醍醐味がない」と采配を振るう上でのやりがいが薄れる点を挙げた。
ヤクルト・髙津臣吾監督は、本拠地の神宮球場が持つ特徴の観点から反対意見を表明。それは、ブルペンが外にあることだった。
「スワローズのいろんな作戦だったり、それがなくなってしまうような気がして。そこの駆け引きが他球場にはない」
広島の新井監督も「戦略や戦術の幅があるのは投手が打席に立つ方だとは思う」と、岡田氏と同じ考えを持っていた。
また、経営を圧迫するのではという意見もあるという。プロ野球を長年取材しているスポーツライターは以下のように解説する。
「コーチ経験者や球団運営に関わっている方から聞くのが人件費面です。例えば『DH制度があるから』と外国人選手を獲得するには億単位の資金が必要になります。
仮にFA市場に打力のある選手が出ても同様ですよね。確かに球団の収益は上がっていると言えども、パ・リーグのような大企業が親会社とも限らないので、そう考えるのではないでしょうか」
今後も議題に挙がるであろう、セ・リーグのDH制導入。果たして変革となるのか、それとも伝統を重視するのか。その決断の先に注目が集まる。
記事/まるスポ編集部